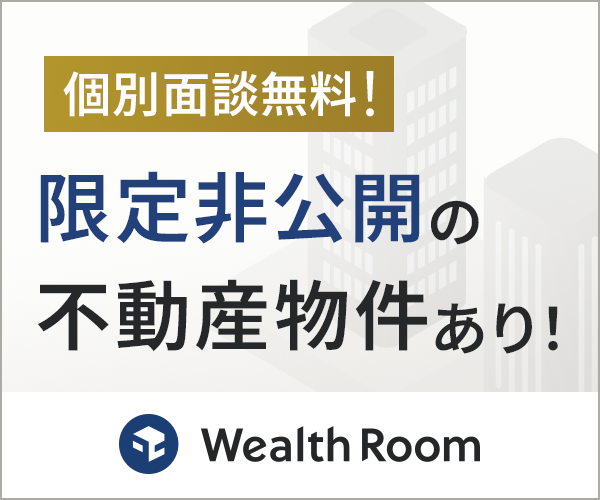株やFXといった投資と比べると、リスクが小さいことが大きな魅力の不動産投資。
しかし不動産投資には、他の投資にはみられない特有のリスクがあるのも事実です。
不動産投資に興味はあるものの、こうしたリスクが怖くてなかなか一歩踏み出すことができないでいる方々も多いのではないでしょうか?
しかし不動産投資のリスクには対策が用意されており、現に成功者は共通して万全のリスクヘッジ(リスクに備えること)をしています。
当記事では不動産投資のリスクと、失敗しないための「リスクヘッジ」法をわかりやすく解説しますので、不動産投資をする際の参考にしてください。
目次
1. 不動産投資のリスクは高いのか?

投資というと、お金が得られる反面「リスクがある」というイメージを持っている人も多いのでは?
株・FX・投資信託などさまざまな投資がありますが、中でも不動産投資のリスクは高いのでしょうか?
不動産投資のリスクは投資の中では比較的低い
不動産投資は、比較的リスクの少ない投資だといわれます。
なぜなら、資産として所有できる物件に投資するからです。
最悪の場合、物件を売却することでリスクの軽減を図ることができます。
しかし、投資である以上リスクが発生する可能性は避けられません。
思わぬリスクにより足下をすくわれることがあるのです。
したがって不動産投資で大切なのは、あらかじめ想定されるリスクを理解し、リスクを回避するための対策を講じておくこと。
「備えあれば憂いなし」が、リスク回避の最善策といえます。
2. 不動産投資で起こり得る10種類のリスクを解説

不動産投資は家賃収入がなくなってしまったり、ローン返済が滞ることによって運用が立ち行かなくなってしまい、失敗するリスクがあります。
不動産投資で発生しやすいリスクを大きく分けると
- 経済的リスク
- 運用していく上で起こるリスク
- 物件に潜むリスク
の3つに分けることが出来ます。
| 外部の経済要因によるリスク | 運用していく上で起こるリスク | 物件に潜むリスク |
| 金利上昇リスク 不動産管理会社の倒産リスク |
空室・家賃滞納リスク 災害リスク |
資産価値の下落リスク 経費がかさむリスク 瑕疵・事故物件リスク |
上記7種類のリスクがどんなものかをご紹介しましょう。
①空室リスク・家賃滞納リスク
不動産投資は家賃収入を要とした投資法なので、空室リスクで家賃収入が途絶えることは最も避けたいリスクと言えます。
空室や家賃滞納が起こると、想定している家賃収入がなくなるので、返済計画に大きな狂いが生じます。空室リスクが返済リスクにつながるのです。
また家賃滞納については、日本賃貸住宅管理会社協会HPによると家賃滞納率の全国平均は6.8%とされています。
新しい入居者を募集するわけにもいかないので、空室リスクよりたちが悪いといえるでしょう。
なぜなら、法律では入居者を優遇しているため、家賃を支払わないからといって、すぐに退去させることは難しいからです。
なかには、数ヶ月家賃を滞納したあげく夜逃げするというケースも少なくありません。
②瑕疵・事故物件リスク
重大な瑕疵がある物件を購入してしまった結果、入居者に敬遠されてしまい、思ったように家賃収入が得られなくなるというリスクがあります。
瑕疵とは欠陥のことで、「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」に分かれます。
物理的瑕疵とは、雨漏りなど建物自体の欠陥。
心理的瑕疵とは、過去に入居者が自殺した、反社会的勢力の事務所が近くにあるなど入居者が精神的に抵抗を感じるような欠陥です。
心理的瑕疵があるとされる代表的な物件のことを「事故物件」と言うことはご存知の方も多いでしょう。
事故物件を購入してしまった場合も、空室にすることもできないので、大幅に家賃を下げることになります。
瑕疵物件は空室になったり、家賃を下げたりするリスクを負うので、想定した家賃収入が望めなくなるのです。
③資産価値下落リスク
不動産投資の資産価値下落リスクとは、建物の経年劣化や周辺環境の変化などにより、土地や建物の資産価値が下落し、価格が暴落してしまったり、家賃を安くしなければならないようなリスクを言います。
家賃は資産価値の下落により、築10年で5~10%、築20年で20%程度下がるといわれています。
いかに立地が良くても老朽化の進んだ物件では高い家賃は望めません。
建物の老朽化以外にも、周辺環境の劣化(近くの大学が移転してしまった、大型ショッピングセンターがつぶれてしまったなど)により賃貸需要が少なくなるようなケースも資産価値の下落を招くことに。
④金利上昇リスク
投資物件を購入する際には多くの人がローンを組んで行いますが、政府の施策で金利が上昇することによって、ローンの返済を圧迫してしまうリスク。
ローンの金利には、「固定金利型」と「変動金利型」があります。
固定金利型は、返済期間の全般に渡って金利が変わらないので計画的に返済しやすい金利型です。
変動金利型は、返済の途中で金利が変わることがあるので金利上昇の可能性があります。
現在は低金利なので、一般的に変動型の方が低金利ですが、金利上昇リスクを負う可能性が高まります。
たとえば、2,000万円の借入で金利が1パーセント上昇すれば、月々1万円程度の負担増になることもあるのです。
⑤経費(税金・管理修繕費など)がかさむリスク
不動産投資には、投資物件の維持費が欠かせません。
経費が思った以上にかさんでしまい、お金が足りなくなってしまうというリスクも起こり得ます。
お金をかけたくないからといって、定期的なメンテナンスやリフォーム費用を投じて物件自体の経年劣化を防がないと、先述の資産価値下落リスクや家賃下落につながります。
マンションで不動産投資をしている場合、管理を管理会社に委託していれば管理費や修繕積立金が毎月必要。
内部の設備が故障して、急に設備の交換費用がかかるといったこともあります。
不動産を所有している人は、毎年固定資産税や都市計画税を納めなければなりませんし、利益を得れば、確定申告で所得税の納付も必要です。
不動産投資ではランニングコストがかかることを覚えておかないと、返済不能に陥るリスクが高くなってしまうでしょう。
⑥災害リスク
不動産投資では災害リスクにより投資物件が倒壊・損壊することも考えられます。
建物自体が壊れてしまっては入居者から家賃を得るどころか、莫大な修繕費がかかってしまうので、ローンは返せなくなってしまうというリスクがありますね。
特に木造アパートの場合、RC(鉄筋コンクリート)造に比べて構造が弱いので、地震で倒壊しやすい、火災が起きやすいなど災害リスクは高くなります。
海の近くであれば津波の心配、川が近ければ氾濫して浸水、山の近くであれば、崖崩れしてしまう危険性があります。
このように、災害リスクは物件を購入する時点で抱えてしまうものです。
⑦管理会社の倒産リスク
副業として不動産投資している場合は、本業が忙しいため管理会社に管理委託していることが多いでしょう。
しかし、管理会社が倒産してしまうこともあり、家賃が回収できなくなるリスクもあります。
管理会社の倒産は、まさに想定外のリスクといえるでしょう。戸数が多ければ多いほど受ける損害額は大きくなります。
管理会社からの家賃の支払いが遅れるような場合は注意してください。
3. 不動産投資で失敗を防ぐためのリスクヘッジ方法

将来は不確実で何が起こるかわからないというリスクがあります。
失敗してしまう可能性を予測してどのようにしたらリスクを回避できるか、リスクによる被害を最小限にできるか、予め備えておくことを「リスクヘッジ」と言うのです。
そして、不動産投資におけるリスクヘッジとは、あらかじめ想定される先述のリスクを回避する事前対策のことです。
不動産投資にはリスクがありますが、それぞれにリスクヘッジ法があるので解説します。
立地のよい物件選びをする
空室リスクを回避するためには、物件購入時に立地の良い投資物件を選ぶのが最善の方法です。
賃貸需要のある所に入居者が集まるのは当然なので、不動産投資成功の80%は立地にあるといわれています。
そのため、事前に交通アクセスや周辺の施設(ショッピング利便性・工場や学校などの入居希望者)について情報を収集するだけでなく、自ら足を運んで住民層を含む周辺環境や物件の状態を確認することが重要です。
また、立地の良い物件を選ぶことで資産価値下落リスクをも防ぐことができるのです。
入居者審査を厳しくしたり、保証会社を利用する
家賃滞納リスクに対しては入居審査の段階でチェックを厳しくするのが有効です。
収入のみでなく勤め先の信用度なども合わせて判断してください。
また管理会社に委託していると、滞納家賃回収のノウハウがあるので効果的です。
日本の法律は借主優位になっていることもあるので保険料は必要ですが、
家賃保証会社を連帯保証人にして家賃を立て替え払いにするか、家主代行システムの利用を考えるのも一つの手です。
金利上昇リスクは固定金利の選択で避けられる
現在の金利水準を考えると、将来は上昇しても下がる可能性は低いので変動金利ではなく、固定金利で契約することをおすすめします。
不動産投資ローンは、長期にわたって返済するので、たった1%でも金利負担は投資家にとって大きなリスクです。
超低金利政策がいつまで続くかによって、今後の金利上昇の対策も変わってくるため、不安に思う方も多いことでしょう。
大切なのは、金融機関によって金利をはじめとする融資条件が異なるため、複数の金融機関と相談して比較することです。
メンテナンスやリフォームで資産価値低下を抑える
不動産投資は長期間の投資になるため、建物の経年劣化による資産価値低下は避けられません。
定期的なメンテナンスやリフォームにより建物の状態を維持するのがポイントでしょう。
賃貸の場合、購入とは異なり築年数や構造よりも見かけで決める人が少なくないからです。
また、立地や環境については、購入時だけではなく将来的な展望も検討してください。
災害へのリスクヘッジ
火災保険や地震保険に加入する
不動産投資では、火災保険や地震保険に加入してリスクに備えることは必須といえます。
ただ注意しなければならないのは、火災保険だけでは地震列島と呼ばれるくらい日本で多い地震が免責となるので別途地震保険に加入することを忘れないようにしましょう。
丈夫な地盤・建物を選ぶ
地震リスクに備えるなら、1981年6月以降に建築確認を受けた「新耐震基準」の建物を選んだ方が良いでしょう。
RC造の物件であれば地震や火災に強いだけではなく、耐用年数が長いのでローンの支払期間も長くなります。
また、建物が丈夫でも地盤が弱ければ傾くかもしれません。
また、津波や川の氾濫で浸水してしまうリスクもあるので、ハザードマップなどを用いて、場所も慎重に選ぶと災害リスクば万全といえます。
ローン返済ができなくなってしまうリスクに備え、資金には余裕を持つ
上述の通り、不動産投資では税金や管理費・修繕積立金・修繕費などさまざまなお金がかかってきます。
毎月のキャッシュフローを管理して、修繕費に加え家賃収入が途絶えた時に備えて、多めに資金を手元に確保しておきましょう。
建物の経年劣化は空室リスクを高め、手取り家賃収入の減少を招くので修繕は避けられません。
そのため、必要経費として毎月の家賃収入から積み立てをすることを忘れないようにしましょう。
管理会社はよく調べて選ぶ
不動産管理会社倒産のリスクを回避するためには、何といっても「倒産しない管理会社」を選ぶことが重要でしょう。
サブリース契約を結ぶ場合も含めて、管理会社が倒産するリスク対策としては、入居率や会社の規模を調べるほか、帝国データバンクの活用や、ネット上の口コミで確認しておくなど、リサーチを怠らないことです。
分散投資をすることを検討する
不動産投資における分散投資とは、投資先を複数に分散することによるリスクヘッジのことを指します。
災害リスクの分散や、所有物件の稼働率低下によるキャッシュフローの悪化、ローン返済の遅延による担保物件差し押さえを回避するための手段です。
賃貸の部屋のタイプを変える
単身者はワンルームや1K・1LDKを好むのに対し、ファミリーは2LDK以上を希望します。
入居者を限定するのではなく
- 複数室あるいは1棟丸ごと購入する
- マンション・アパートの1室を区分所有する
- 店舗や駐車場など居住用以外の用途に変更する
なども考えましょう。
築年数や投資時期が違う物件を購入する
修繕費を積み立てるとはいっても、実際に修繕を実行するとなると、キャッシュフローが一時的にしろ悪化します。
物件の築年数や購入時期をずらすことで修繕支出の分散を図ることが可能です。
投資場所の地域を別々にする
不動産投資する際に都心と郊外といったよう地域を分けることは、有効なリスクヘッジとなります。
また同じ都心でも若年者が多い地区とファミリーや単身赴任者が混在する地区、場合によっては海外まで視野に入れて投資物件の地理範囲を分散することで、将来の地価下落への対策ができるのではないでしょうか。
不動産以外の投資をする
修繕費積み立てやローン返済に回した余裕資金を使いきってしまうのではなく、投資信託(不動産を対象にしたものがREITです)・株式・FXに再投資するなど複利で増やすことも視野に入れましょう。
4. 不動産投資のリスクはリスクヘッジすることで極限まで抑えられる!
不動産投資は投資額が多いので、リスクに対してあらかじめリスクヘッジを検討しておかないと損失額が大きくなるのです。
ただ、リスクヘッジさえ行えば、不動産投資の成功率は数倍にも、数十倍にもなります。
まずは、リスクに対する知識を身につけてください。
また不動産投資のリスクやリスクヘッジについてもっと詳しく知りたい場合は、MIRAIMO無料オンライン相談でお問い合わせください。
MIRAIMO公式アカウント友だち登録
不動産投資の実践では大きなお金が動くので、専門家のアドバイスを受けることが欠かせません。
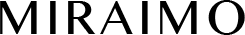
 フォロー
フォロー 友達になる
友達になる

 RSS
RSS
 不動産投資の基礎
不動産投資の基礎 不動産・収益物件の購入
不動産・収益物件の購入 不動産投資でかかる経費・税金
不動産投資でかかる経費・税金 不動産投資でよくある失敗やリスク
不動産投資でよくある失敗やリスク 不動産のローン・融資
不動産のローン・融資 不動産の管理・運用
不動産の管理・運用 不動産の売却
不動産の売却 MIRAIMO不動産セミナー・ニュース
MIRAIMO不動産セミナー・ニュース Twitterをフォローする
Twitterをフォローする Facebookでファンになる
Facebookでファンになる RSSを購読する
RSSを購読する